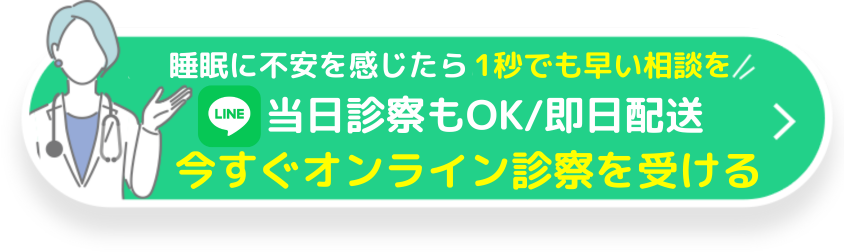夢を見ると、朝目を覚ましてもスッキリしないと感じる方もいるのではないでしょうか。
夢ばかりみて寝た気がしないというお悩みを解決するために、本記事では、眠りが浅い、また熟睡できない原因、また精神状態や改善策について解説します。
朝起きても熟睡できてないと感じる方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
夢ばかり見て寝た気がしないのは病気?
夢ばかり見て寝た気がしないのは、病気である可能性も考えられます。
可能性のある病気は、睡眠時無呼吸症候群、むずむず脚症候群、うつ病などです。
とくに、睡眠中のいびきや無呼吸、起床時の疲労感や倦怠感、頭痛、日中の眠気、抑うつなどの症状が見られる場合は、病気の可能性があるため、医師に相談しましょう。
しかし、必ずしも病気であるというわけではありません。
病気以外で考えられるのは、ストレスや体調不良などにより眠りが浅いことです。
一般的に、深い睡眠である「ノンレム睡眠」、浅い睡眠の「レム睡眠」のうちレム睡眠時に夢を見ることが多いです。
健康な人をレム睡眠期に覚醒させると約80%の割合で夢を見ていたと話すことから、レム睡眠は夢を見る睡眠段階と考えられています。ただし、ノンレム睡眠の時にもわずかながら夢を見ます。
引用:厚生労働省
上記のように、レム睡眠中で夢を見る人は多くいることが報告されています。
つまり、夢ばかり見ている人は、レム睡眠が長くなっている状態で脳が休んでいない時間が長いということにあります。
そのため、脳で作られる脳脊髄液がうまく循環できず、頭痛や集中力の低下などの原因となるでしょう。
眠りが浅いレム睡眠が続くと疲労回復しづらく、体調を崩しやすくなるでしょう。その結果、悪夢を見やすくなるといわれています。
病気のケース
夢を見る原因が病気の場合、考えられるのは以下の病気です。
- 睡眠時無呼吸症候群
- うつ病
- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)
睡眠時に眠りが浅くなる原因として病気である可能性が考えられます。
寝ている間は無自覚であるため、病気に気づきづらいですが、中には病気が潜んでいる場合があります。
寝れずに困っている場合は、睡眠薬から初めてみることで睡眠の改善が期待できることがありますので、まずはクリニックなどに相談することがおすすめです。
睡眠に不安を感じたら
オンラインで不眠相談を
- オンラインで処方から発送まで
- 定期的に睡眠薬が購入できる
- 診察料が無料で相談できる
病気の疑いが低いケース
しかし、夢を毎日見ることは必ずしも病気であるとはいえません。
病気以外に考えられるケースは以下のとおりです。
- ストレスが溜まっている
- 就寝前に飲酒やカフェインを摂取している
- 体内時計のリズムが乱れている
- メラトニンが減少している
- 睡眠環境が劣悪である
とくにストレスや心理的不安を抱えている方は多く、影響も大きいと考えられます。日常生活における人間関係やプレッシャー、ハードスケジュールなどは、夜間の脳活動に影響を与えて夢の増加に繋がります。
もし、症状が一時的で、ほかにも大きな問題が考えられない場合は、日常生活の見直しやストレス管理をすると、改善につながるでしょう。
夢ばかり見て熟睡できていない時の症状
夢ばかり見ている原因がわかっても、眠っている間は意識もないためどのような症状が現れているか確認しづらいでしょう。
夢ばかり診て熟睡できていないときの主な症状は以下のとおりです。
- 眠りが浅く夢ばかり見る
- 一瞬で朝になり寝た気がしない
- 寝ているはずなのに疲れる
- 熟睡できておらず、途中で目が覚める
以下では、それぞれの症状について解説します。
眠りが浅く夢ばかり見る
眠りが浅く夢ばかり診ていると熟睡できていないということになります。
眠りが浅いということは、レム睡眠の時間が長く、ノンレミ睡眠の時間が短いということです。
レム睡眠が長くなる理由には、ストレスや不安、心配事などの心理的不安や環境の変化などが考えられます。眠りが浅いことがわからない方は、以下の症状がないか確認しましょう。
- 小さな物音でも起きてしまう
- ずっと悪夢を見ている
- 次の日になっても夢の内容を覚えている
- 尿意で目を覚める回数が多い
上記に当てはまる方は、眠りが浅い傾向にあります。
細菌夢ばかり見ているなと感じる方は、眠りが浅い原因について考えてみましょう。
一瞬で朝になり寝た気がしない
一瞬で朝になり寝た気がしないと感じる方もいるでしょう。深い睡眠が得られず、質の低い睡眠になるとすぐに朝になったと感じることがあります。
一瞬に朝になり寝た気がしないという時の自覚症状は以下のとおりです。
- いつも泥のように眠っている
- ちょっとやそっとで起きない
- 眠る前に何をしていたか思い出せない
- 寝ているはずなのに疲れが取れていない
- 体が一日中だるい
- 頭痛がする
寝た気がしないことは夢を見ていることや日頃のストレス、生活習慣などが影響している可能性があります。
長期間に渡って上記の状態が続くと、日中の集中力の低下や機能の低下、心身への健康に悪影響が現れるでしょう。
寝ているはずなのに疲れる
睡眠時間は十分なはずでも、次の日に疲れが残っているということもあるでしょう。
寝ているはずなのに疲れているという方が感じられる自覚症状は以下のとおりです。
- 睡眠時間は十分なのに次の日に疲れが残っている
- ベッドから起き上がれない
- なぜかどっと疲れている
- 寝た気がしない
- 体が一日中だるい
睡眠時間は十分でも朝起きるのがだるかったり、仕事中に集中力がなかったりする場合は、熟眠障害という不眠症である可能性が考えられます。
眠れていないことを自覚する不眠症もありますが、眠っているのに眠れていない感覚がある「熟眠障害」は自覚しづらいこともあります。
休日にたくさん寝て回復しようとしている方も熟眠障害の傾向があるため要注意です。
熟睡できておらず、途中で目が覚める
熟眠できずに途中で目が覚める場合、深い眠りが維持されておらず、断続的な睡眠サイクルが影響している可能性があります。
途中で目が覚めることにより、睡眠の質が低下して、朝起きた際に疲れや不快感を感じるでしょう。
熟眠できずに途中で目が覚めるという具体的な自覚症状は以下のとおりです。
- 何故か分からないが夜中に目が覚める
- 物音やトイレが原因でないのに目が覚める
- 普段の考え事を思い出して急に焦燥感に駆られる
上記のような症状がある場合は、熟眠できていない可能性が高いでしょう。
睡眠障害と思ったら
オンラインで医療用睡眠薬を
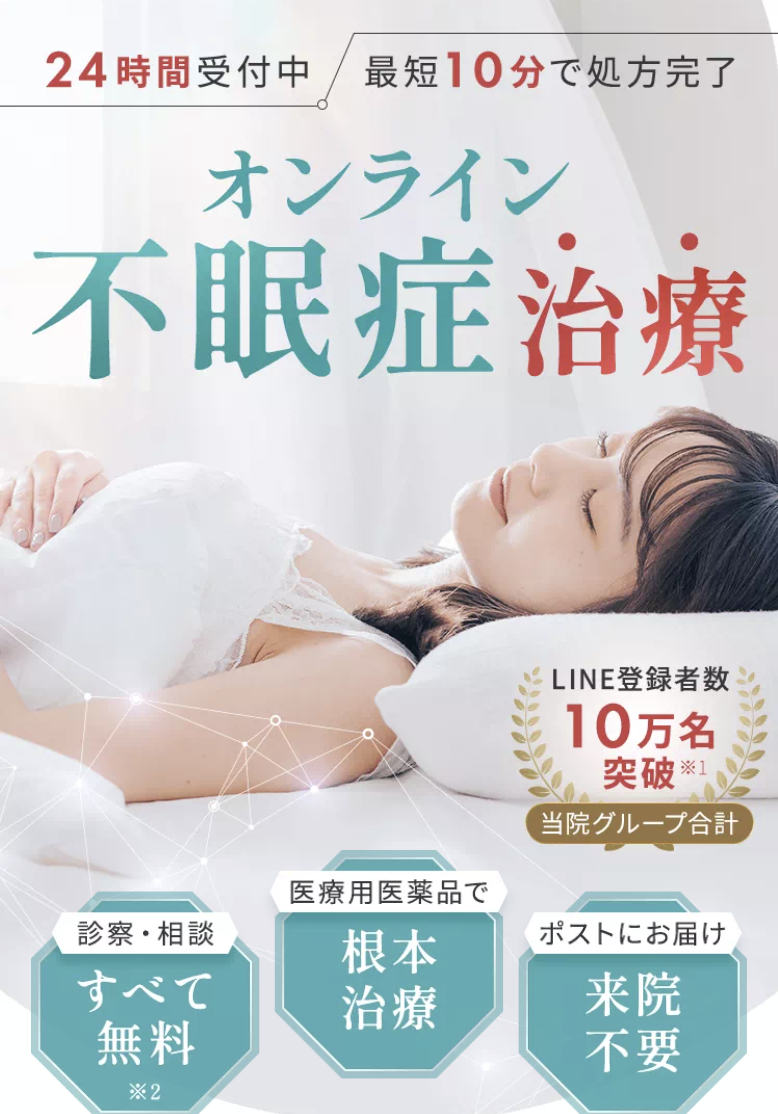
- 依存性の少ない睡眠薬
- 入眠障害から中途覚醒まで対応
- 1日一回の服用で睡眠治療
熟睡できていない原因や理由は?
熟睡できていない原因や理由は、個人により異なります。
原因と理由を理解しておくことで、改善しやすくなり睡眠の質向上を目指せるようになります。
- ストレスが溜まっている
- 就寝前の飲酒やカフェイン
- メラトニンが減少している
- 睡眠環境が劣悪である
- 睡眠時無呼吸症候群
- うつ病
- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)
以下では、各問題の具体的な内容や症状、傾向について詳しく解説します。
ストレスが溜まっている
毎日夢を見る場合、昼に溜まったストレスを脳が寝ている間に処理していることが考えられます。
ストレスや心の不安がある場合は、浅い睡眠が続くことが多く、過度のストレスは寝付きの悪化や途中覚醒を引き起こして夢を見ることが多くなるでしょう。
ストレスが続くと、交感神経が優位になり、リラックスして眠るのが困難です。そのため、睡眠の質や深さを低下させて、夢を多く見るようになります。
ストレスが溜まっている時に起きやすい症状は以下のとおりです。
- 失敗を何度も思い出してしまう
- いわれたことやされたことを何度も思い出してしまう
- 怒り心頭でこんなことされたらこうしようと対応策を考えてしまう
上記のような症状は、進学や就職してからの5〜7月や破局や大きいなミスをした直後にありがちです。
ストレスを溜めすぎる、また人に相談できずにストレスが発散できていない状態が続いてしまうと、うつ病になる可能性があります。
ストレスにより眠れないと感じている方は、日光を浴びる、体を動かす、趣味を見つけるなど気分を変えられるようなことを見つけてみましょう。
就寝前の飲酒やカフェイン
寝る前の飲酒やカフェインが含まれる飲み物を摂取すると夢を見る原因となります。
少量のアルコール摂取は、脳内の抑制神経伝達物質であるGABAが増加して、ドーパミンやノルアドレナリンが減少して眠くなります。しかし、同時に眠りを浅くする効果もあり、過剰摂取するとより睡眠の質が悪化するでしょう。
また、コーヒーや紅茶などカフェインが含まれている飲み物を摂取するのも夢を見る原因です。カフェインは中枢神経を興奮させる作用があり、過剰摂取すると興奮状態を引き起こします。
そのため、脳が休めず浅い眠りを引き起こして、夢を見るようになるでしょう。
睡眠の質改善のためには、寝る前の飲酒やカフェインの摂取は避けるようにしてください。
寝る前は、自律神経を整える作用があるホットミルクやリラックス効果があるハーブティー、血流を良くするには水をコップ一杯に飲むといいでしょう。
体内時計のリズムが乱れている
体内時計のリズムが乱れていることも夢を見る原因の一つです。
体内時計とは、自然の光と暗闇や日々の生活リズムにより調整されて、健康な睡眠に影響があります。
不規則な生活習慣や夜更かし、夜遅くまでスマホやパソコンを使用すると、体内時計を乱して寝付きを悪化させ、結果的に夢を多く見るようになります。
体内時計のリズムを整えるためには、なるべく一定時間に眠れるように時間を決めておきましょう。
毎日7〜8時間眠ろうと決めている方もいますが、具体的に眠る時間を決めることのほうが大切です。
24時に就寝して7時には起きる、また25時までには眠るなど時間を固定しましょう。
就寝時間と起床時間を決めておくと、習慣がついて体内時間のリズムも整います。
メラトニンの減少
夢を見る原因としては、メラトニンの減少が挙げられます。
メラトニンは、体内時計を調節して睡眠の質を向上させる重要なホルモンです。
夜になると脳内の松果体から分泌されるメラトニンは眠気を促して睡眠の質を良くします。しかし、不規則な生活習慣やスマホ・パソコンの使用により、メラトニン分泌が減少する場合があります。
メラトニンが不足すると、入眠が困難になり、深い眠りに影響を及ぼし、夢を見てスッキリしない目覚めを引き起こすでしょう。
メラトニンの減少を防ぐには、日光を浴びることが大切です。毎朝日光に浴びるとメラトニンの分泌を停止させられます。
また、メラトニンは14〜16時間後に再分泌されるため、23時に眠る場合は、7〜9時に起きて日光を浴びるようにしましょう。
睡眠環境が劣悪
睡眠環境が劣悪であると、レム睡眠が増えて夢を見るようになります。
寝る前に食べ物を食べたり、布団に入ってからテレビやスマホを使用すると睡眠の質低下に繋がります。
寝る前に食べ物を食べると、消化するために内蔵に血液が集まり、脳への血流が生きにくくなりレム睡眠を引き起こすでしょう。そのため、寝る2時間前には食事を済ませておきましょう。
また、睡眠環境で枕が自分にあっていない、外から騒音が聞こえるなども睡眠の質を下げる原因です。少しでも睡眠環境にストレスを感じている場合は、環境の見直しをしましょう。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、眠っている間に呼吸が一時的に止まって、無呼吸の状態を繰り返す病気です。無呼吸になると、体が低酸素状態となり苦しい状態がつづきます。
無呼吸の状態は自分で気づいていなくても、一瞬目を覚ましています。無呼吸になり苦しいと感じた気持ちが、悪夢を引き起こす原因です。
睡眠時無呼吸症候群に気づくためには、以下のポイントを確認しましょう。
- いびきや無呼吸を指摘された
- 睡眠事時むせることがある
- 途中で目が覚める
- 寝汗をかく
- 起床時に口が渇いている
- 起床時に頭痛があるなど
上記のようなある場合は、とくに睡眠時無呼吸症候群の疑いがあります。
睡眠時に違和感を感じた場合は、医師に相談して検査と治療を受けましょう。
うつ病
また、うつ病の場合でも、夢を見る機会が増えます。うつ病の場合、レム睡眠を抑える仕組みが働かなくなり、レム睡眠が早い時期に出現する傾向にあります。
その結果、眠っている途中で目覚める途中覚醒が増えて、夢を見るようになるでしょう。
うつ病の疑いがあるサインは以下のとおりです。
- 以前よりも元気がない
- 体調不良が増える
- 仕事や家事でのミスが増える
- 周囲との交流を避ける
- 遅刻、早退、欠勤、欠席が増えるなど
うつ病は、睡眠時の眠りの浅さを引き起こすだけでなく、体調不良や心の不調を引き起こします。
憂鬱な気分や何に対しても興味がわかない症状がある場合が、1日中、2週間異常続いている場合はうつ病の疑いがあります。
うつ病の可能性がある場合は、心療内科や精神科医で医師に相談して、診断を受けてみましょう。
むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)
むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)でも、夢を見ることが多いといわれています。
そもそも、むずむず脚症候群とは、寝る前になると脚がムズムズしだして入眠できない病気です。むずむず脚症候群の場合、睡眠している状態でも症状が現れることから、睡眠が浅くなり悪夢を引きおこす場合があるでしょう。
むずむず脚症候群を改善するには、足のマッサージやシャワー・入浴による温熱刺激が効果的です。
シャワーや入浴による温熱刺激は、むずむず脚症候群を軽減しますが、適切な温度は個人により異なるため、症状が軽くなる温度を確認しておきましょう。
眠りが浅い状態が長く続く場合の改善策
眠りが浅い状態が長く続くと、病気に繋がる可能性があります。
病期を発症してしまうと、さらに治療に時間がかかり、仕事や学校を休まなければいけないということも考えられます。
眠りが浅い状態が続く場合は、睡眠薬を利用しましょう。睡眠薬を利用すると睡眠時によく眠れないお悩みを改善できます。
万が一、改善策を実行しても良くならない場合は、病期のケースも有るため、然るべき機関で診察を受けましょう。
睡眠薬を試してみる
睡眠にお悩みがある場合は、睡眠薬を利用しましょう。睡眠薬を利用すると、あらゆる不眠症二高架が期待でき、ぐっすり眠れるようになります。
睡眠薬の処方におすすめなのが「CUREA CLINIC」です。
CUREA CLINICは、クリニックに足を運ばなくても、LINEで友だち登録するだけで処方してもらえます。
CUREA CLINICで処方してもらえる睡眠薬は「デエビゴ」です。デエビゴは、オレキシン受容体拮抗薬に分類されている新しい睡眠薬です。依存も少なく、入眠困難にとくに効果があります。
中には、睡眠薬を利用したくても病院に行く時間がなくて諦めている方もいるでしょう。
しかし、CUREA CLINICはLINEを利用すれば自宅や職場でも場所を選ばずいつでもどこからでも利用できます。
診察を受けて、決済完了すれば、翌日にはお薬が配送されてすぐに薬を受け取れる点でも魅力です。
相談も無料で実施されているため、睡眠薬がほしい方や睡眠に関して相談したいとお考えの方には「CUREA CLINIC」がおすすめです。
途中覚醒や入眠障害におすすめのクリニック
途中覚醒や入眠障害でお悩みの方には「あしたのクリニック」がおすすめです。
あしたのクリニックでは初めて受診した方の90%以上がとても良かった・良かったと回答しています。
あしたのクリニックは、対面式のクリニックで、精神科専門医・指導医の資格を持つ先生により適切に診断してもらえます。
不眠症や睡眠障害、寝付きの悪さなど、不眠症・睡眠障害の幅広いお悩みにも対応しているため自分に合う改善法を見つけられるでしょう。
睡眠薬を処方も初診から対応しており、また、仕事を休みたいとお考えの場合は、給食の際に利用できる診断書を当日発行してもらえます。
オンライン診療よりも対面で医師の目を見て診察してもらいたいとお考えの方には「あしたのクリニック」がおすすめです。
熟睡できない場合は医師に相談をしてみよう
本記事では、眠りが浅い、また熟睡できない原因、また精神状態や改善策について解説します。
夢を見るときは、睡眠が浅くレム睡眠の時間が長いです。
人により熟睡できない原因は異なりますが、主な原因は以下のとおりです。
- 眠りが浅く夢ばかり見る
- 一瞬で朝になり寝た気がしない
- 寝ているはずなのに疲れる
- 熟睡できておらず、途中で目が覚める
また、上記以外にも病気により睡眠の質が低下している可能性があります。
病気として考えられるのは以下のとおりです。
- 睡眠時無呼吸症候群
- うつ病
- むずむず脚症候群(レストレスレッグス症候群)
睡眠時はとくに意識がないことから病気に気づきづらいです。そのため、少しでも違和感を感じたら医師に相談するように心がけましょう。
また、睡眠にお悩みがある場合はクリニックで睡眠薬を処方してもらいましょう。
オンラインクリニックで処方してもらいたい方には「CUREA CLINIC」、対面で医師に診察してもらいたい方は「あしたのクリニック」がおすすめです。
まずは、自分の眠れない原因を突き止めて、適切に治療して睡眠の質向上に努めましょう。